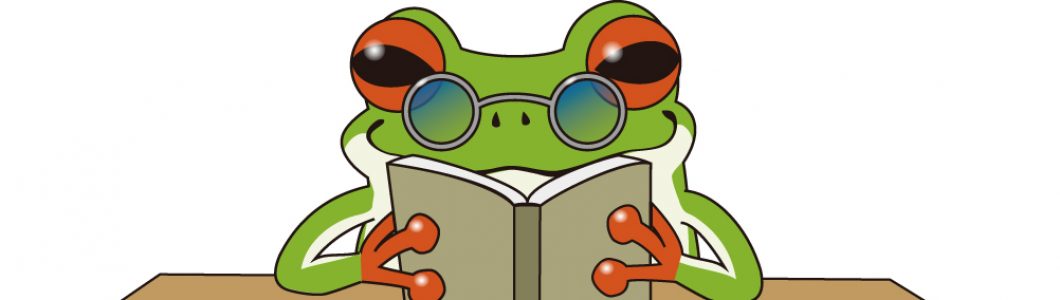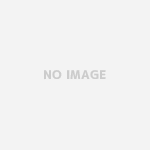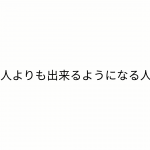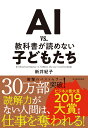こんにちは、かいとんです。
最近に限らずよく相談されるのが、
『勉強のモチベーションが上がらないのでどうしたらいいですか?』
というものです。
で、詳しく聞いてみると
休日は10時間勉強しようと思っているのですが続かなくて・・・
とか、
何10回も長文を書き写しているんですが、なかなか覚えられなくて・・・
だったり、
長時間机について勉強ができません。
なんてことを言われます。
そんな人たちに私が思うことは、
そんなキツイだけで結果が出ないやり方をして・・・ドMですか?(´・ω・`)
と。
まぁ、口は悪いですがそんなことを思います。
出来る人は知っている、か、無意識にやっている。
出来ないのは知らないだけ。
「楽して早い」方法があるなら、そっちのほうが良いですよね?
この記事では、『「楽して早い」方法』について書いてあります。
ちょっと長い記事なので、移動中や休憩時間などの時間があるときに読み進めてもらったらいいかなと思います。
最初は目次だけ。
次は各項目を。
そんな感じで何度も目を通してください。
回数を重ねることで、大切なことが定着しやすくなります。
また、コメント欄はメモ代わりに使ってください。
どこどこまで読んだ。や、こう思った。などで構いません。
では、最後までお付き合いください。
頑張るに対する間違った思い込み
私の指導を受け始めたばかりの生徒からよく聞くセリフがあります。
『頑張らないと』
それに対して私は、
『頑張るってどういうことだと思ってる?』
と、聞くわけですが…、
だいたいどの生徒も、結果を出すためには、
一生懸命に何でもかんでも全力投球をして、
鬱々するくらい考えこみながら、
学校や塾の先生の言うとおりにやらなくてはいけない!
なんて思ってます。
しかし、この『頑張る』は曲者で、
『頑張る』方法を間違えると永久に結果が出ません。
そして、先生には
『この頑張った経験がいつか活きるよ』(←これ、最高の責任逃れだと思いません?)
なんて、無責任かつ何の救いにもならないことを言われたりするわけです。
どんなに努力をしても報われない努力というものはあるわけですが、
私自身、成功するための方法について勉強していますし、
それに加えて、けっこうな数の生徒を見てきましたから、自分の勉強した成功法則がある程度正しいという自信があるわけです。
成功する生徒と、結果が出ない生徒のどこが違うのか?
ここで結論を行ってしまいますが、
成功する生徒は「楽して早い」やり方をしています。
そんなもん、能力が高いから楽しても早いんじゃないの?
なんて言われそうですが、そんなことはありません。
実際、自分の生徒にはその「楽して早い」やり方を徹底させて、結果が出ているわけですからね。
じゃあ、結果に繋がらない努力と、「楽して早い」やり方はどう違うのか?
ザックリとみてみましょう。
結果に繋がらない努力と「楽して早い」やり方の違い
結果に繋がらない努力
一生懸命頑張るがやり直しが多い
「楽して早い」やり方
一発で決める
結果に繋がらない努力
全てに全力投球で、疲れ果てる
「楽して早い」やり方
スパッと割り切る
結果に繋がらない努力
責任感を持ちすぎて、やることを抱え過ぎる
「楽して早い」やり方
抱え込まない
結果に繋がらない努力
計画に労力と時間をかけすぎ、疲弊する
「楽して早い」やり方
試験の「枠組み」を利用する
結果に繋がらない努力
先生の指示通りにやるが、結果が伴わない
「楽して早い」やり方
自分で「できる」ようになる
なるべく対になるように並べたつもりですが、出来る人とできない人の違いがわかってもらえましたか?
「楽して早い」やり方とは?
じゃあ、今紹介した「楽して早い」やり方を一つ一つ見ていきましょう。
一発で決める
1問を何も見ないで考えに考え抜いて答えを書くことは大事ですが、受験勉強においては全くと言っていいほど大事ではありません。
それよりも、同じ問題を答えを見ながらで良いので何度もやることの方が大事。
最初は答えを見ながらでないとできない問題が、何度もやっているうちに答えが無くてもできるようになります。
ただし、その時はただ答えを写すのではなく、なぜそうなるのかを自分自身に解説しながら行うことが肝です。
勉強を始めたら、最初から満点が取れる必要はありません。
上で「なぜそうなるのかを自分自身に解説しながら」といいましたが、それも、最初は答えを棒読みするだけで構いません。
最初は棒読みであっても、説明を読んだりしているうちにだんだんと説明できるようになります。
周りの人たちは、無責任にいろいろなアドバイスをくれます。
『あれやった方が良いよ』『これもやった方が良いよ』…全部無視しましょう。
本当に必要なことだけやると、受験勉強でやることはとんでもなく少ないことがわかります。
重要なこととは何ですか?と、よく聞かれますが、『頻出・基本』です。『応用』はそれらができてから考えましょう。
ひとつの問題に何分も使っていると、時間をドブに捨ててしまいます。0から有を生み出すことはとても大変なことです。
入試では、0から有を産み出すことは求められていないので、わからない問題は考えこまずにすぐ答えを確認しましょう。
これは勘違いしている人が多いのですが、テストの採点とは相手の価値観(正解)が優先されます。
自分がどんなに頑張って出した答えであっても、相手が正解だと思わなければ不正解です。
「自分なりにやったんです」は受験において無意味。「相手に受け入れられる」ようにやってください。
スパッと割り切る
苦手科目はあまりやる気が起きません。気づけば得意科目ばかりやっていて、苦手科目は手付かず…
なんてことありませんか?
しかも、その得意科目が入試で使わない科目だったりしたら・・・
また、
「この科目は大好きなんです。点数は取れないけど」
という科目よりも、
『この科目はあまり好きじゃないけど、点数は取れるんですよ』
という科目の方を優先させた方が、最終的に合格に近づくことになりませんか?
「下手の考え休むに似たり」なんていうことわざがあります。
何かアドバイスをもらったとします。そのアドバイスが周りのみんなと似たり寄ったりのアドバイスなら、特に問題なく受け入れるでしょう。
しかし問題は、今まで周りの人に言われたことのないようなアドバイスをされたときです。(特に、先進的な方法で結果を出しているプロのアドバイスはこういうことが良くあります)
ここで失敗する人はなぜか・・・
周りの素人に相談する
わけです。
何も解からない人が何も知らない人に相談する地獄絵図…
私も、明らかにやり方が失敗しているがために結果が出ず悩んでいる人を見るに見かねてアドバイスをさせてもらうことがあるのですが…
まぁ、受け入れられないですね。
やりもせずに、本当ですか?じゃあ今度やってみます。
で、結局やらない。
では、出来る人はどうなのか?
即実行します。
もう、2秒くらいで。
自分の知らない知識が入ってきた時に、そのことについて考えたり悩んだりすることが無駄だということを知っているからです。
と、言うように、悩む暇があったらとりあえず実行しましょう。
悩む前に実行しろとは言いましたが、それはゴールが明確な場合です。
次のテストで…
テスト範囲は…
と、言うようにゴールが明確であることが大前提。
入試の場合は模試の偏差値がゴールではなく、(入試で合格点を取って)合格することがゴールなので勘違いしないようにしましょう。
抱え込まない
- 自分が得意、かつ、自分にしかできないことはなにか?
受験生が得意で、かつ、自分にしかできないこと。
それって、自分の学力を伸ばすための勉強をすることじゃないですか?
家事手伝いなど色々あるとは思いますが、それって本当にあなたじゃないとできないことですか?
本当に自分しかできないことに集中すると、受験勉強に限らず、人生はとても豊かに、そして楽になりますよ。
『整理・整頓』という言葉は聞いたことがありますか?簡単に説明すると、
整理がいるものを残し、いらないものを捨てること。
整頓が残したものを整えることです。
抱え込みすぎて疲れている人はまず、
本当に自分しかできないことと、自分じゃなくてもできること
に整理してみましょう。
試験の「枠組み」を利用する
試験には必ず出題範囲というものがあります。
最も注意しなくてはいけない枠組みは『科目』です。
推薦入試を狙っている人は、全ての科目で良い成績を取る必要があるので、まんべんなく勉強する必要があるでしょう。
しかし、一般入試で受験する人はそうではありません。
特に、大学入試の一般入試では、学校の成績は加味されないことがほとんど。
自分の受験科目だけ勉強していれば大丈夫です。
(とは言っても、卒業する程度の成績は必要です)
過去問に限らず模試など、テスト問題をずっと見ていくとわかるのですが、『必ず』といっていいほど出てくるものがあります。
これが頻出です。
例えば、人称代名詞(Iとかheとかyourとかhersとかそういうやつです)が出てこない英語の文章があるでしょうか?
主語、動詞が出てこない文章は?
数学であれば文字式が出てこないテストがありますか?関数は?方程式は?
と、必ずどのテストにも出てくるものがあります。
この、頻出ができるようになることが、試験で安定して点数を取る第一歩です。
第一歩が無ければ第二歩もないので、頻出をまずはしっかりできるようにしましょう。
- どうやるのか?という質問よりも、ここはどういうやり方でできますか?という質問
わからない問題が出てきた時に、全く考えずにいきなり解き方を聞く…なんてことしてませんか?
わからない問題が出てきた時に大切なことは、自分がどこが出来てどこがわからないのかを明確にすることです。
そうすることで、自分に足りないことが何なのかがわかりますし、質問の効果が高まります。
勉強するときのモチベーションが低下する大きな要因の一つに、『わからないこと』があります。
さぁ、問題を解こう!
と、頑張って問題を前にして、いきなりわからなかったとき、延々と考えこんで結局ギブアップ。
そのままやる気が無くなって勉強を止めてしまう。
そんな経験はないですか?
わからないときは素直に答えを見る。
そして、解説を読みながらとりあえず答えがそうなることを覚える。
それから、わからないことをメモなどにまとめておいて、問題の答えがなぜそうなるのかを先生などに聞く。
こうするだけで勉強のモチベーションが下がることを防げます。
自分で「できる」ようになる
自分で出来るようになる最大のメリットは、何と言ってもプロっぽい素人に引っかからなくなることです。
プロっぽい素人ってどんな人?と思うでしょうが、意外と身近にいます。
そう、塾や学校の先生です。
塾や学校の先生は、教科の内容を教えるプロであっても、勉強法や合格させるプロではないからです。
塾や学校の先生が『こうやって勉強すればいいんだよ』と言ったとします。
でもそれって、その人がやったことであって、本当に理にかなっているのでしょうか?
まぁ、膨大な時間と労力を使ってその方法で合格したとしましょう。
その後の人生で勉強をしようと思ったときに、その方法でまた勉強するんですか?
社会人は学生よりも勉強する時間は短いですよ?
それよりも、自力で「楽して早い」方法を使ってとっとと結果が出る方が良くないですか?
と、こんなことを言っていると
現役時代に全国模試で上位になったことがないやつが何言ってんだ!
なんて言ってくる先生がいます。(いや、ほんとに)
名プレイヤーは名コーチに非ず
なんて言葉がスポーツ界にはありますが、これは勉強の世界も同じです。
現役時代にどんなにいい成績を取ろうとも、理論が間違っていれば生徒を伸ばすことができません。
それはつまり、自分が良い成績を取るプロであっても、生徒に良い成績を取らせるプロではないということですね。
実際、こんなプロっぽい素人が99%です。(大袈裟に言ってますし、数字に根拠はありません)
ということで、あなた自身ができる人になればそういった人に引っかかって時間を無駄にすることがなくなるのです。
自分ができること(問題の解き方)だけを周りの人に話していると、周りの人は『コイツは出来るやつだ』と、思ってくれます。
そうすると、周りの人たちはその問題についてあなたを頼ってくるでしょう。
あなたはその人たちにわかることについて説明をします。
一回目よりも二回目、二回目よりも三回目と、あなたの説明は上手くなります。
説明が上手くなるとともに、あなたの中にその問題は定着していきます。
これが周りに出来るやつだと思われるメリットです。
他人に説明するとき、あなたの脳はフル回転します。
自分の持っている知識を総動員して、さらに、わかりやすくまとめようとします。
しかも、他人に話すことで自然とアウトプットすることになり、アウトプットすることでさらに知識が定着します。
あなたが何かで成功したいと思ったとき、まずやることは成功した人を研究することです。
それは、入試に合格した人に限りません。
短期間で目標を達成した人や、過去の偉人がどういうことをしたのか。どういう考え方をしていたのか。それを研究してください。
それをマネることで、あなたが成功する確率はグッと高くなります。
もし、あなたの身近にあなたがこうなりたいと思うお手本のような人物がいたとすればそれはとても幸運なことです。
あなたがすべきことは、その人となるべくたくさん行動を共にし、会話をし、その人が日常やっていることのマネをして、その人ならこういう時どうするだろうと考えることです。
そうするだけで、あなたはその人と同じような成功をすることができるでしょう。
大切なことは、成功した人と全く同じことをすれば同じように成功できる。
と、言うことです。
マニュアルがあるのなら、そのマニュアル通りにやりましょう。
項目ひとつ残らず忠実に実行してください。
もし、上手くいかないとすれば、あなたがマニュアル通りに実行していないからです。
何か目標を立てたとき、その目標を達成するために計画は不可欠です。
ですが、何かを達成するときには今すぐに行動するくらいの速さが必須です。
計画は途中で変更することがほとんどなので、詳細に作る必要はありません。
まずゴールを明確な数字で設定し、そのゴールを達成するために必要なこととその方法だけを書き出して、大まかな締め切りを設定したら、一つ一つ実行していきましょう。
途中で締め切りに間に合いそうにない時は方法が間違っているか、無理な締め切りを設定した可能性があるので、どちらかを変更します。
計画を考えることにエネルギーと時間を浪費すること、そして、計画通りにいかなかったときにモチベーションが低下することは避けなければいけません。
まとめ
さて、最後まで読んでいただいた方はどう思ったでしょうか?
間違った方法でやってたから、そりゃ上手くいかないよね。
と、感じていただけたなら幸いです。
受験勉強は『苦行』である必要は全くない
「楽して早い」方法で合格出来たらそっちのほうが良いですね。
そのためにはまず、「楽して早い」方法を学ぶ必要があるわけです。
科目の内容は塾や学校の先生に聞けば教えてくれます。その点に関してプロなのは間違いないですから。
では、「楽して早い」方法は?
もちろん、こんな偉そうなことを書いている私も指導していますし、別の先生でもいいでしょう。
私の指導をご希望の方は、私のLINE@
インターネット学習塾『塾講師かいとん』
を、登録してお問い合わせください。